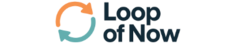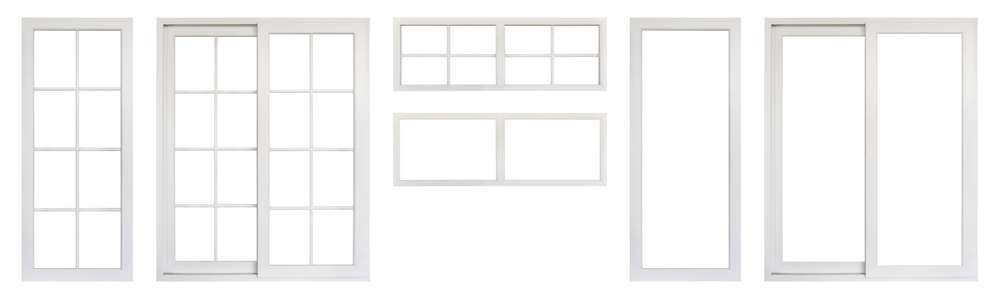2025年に学ぶ日本の放棄された家の取得方法と相続登記のポイント
日本では2024年4月1日から「相続登記」が義務化され、相続で取得した不動産の名義変更は原則3年以内に完了しなければなりません。この改正は所有者不明土地や空き家問題の解消を目的としています。放棄された家を取得する際は、相続関係の調査、戸籍や登記事項証明書など必要書類の収集、相続人の特定、登記申請の正確な手続きと費用見積もりが重要です。本記事では具体的な手続きの流れ、必要書類一覧、注意点、費用の目安、専門家に依頼する場合のポイントまでわかりやすく解説します。

放棄された家を取得するために知っておくべき相続登記の義務化とは
2024年4月から施行された相続登記の義務化により、相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務付けられました。これまで任意だった相続登記が義務化されたことで、所有者不明の土地や建物の発生を防ぎ、不動産取引の透明性を高めることが目的とされています。
放棄された家を取得しようとする場合、まず現在の登記状況を確認し、相続人が存在するかどうかを調査する必要があります。相続人全員が相続放棄をしている場合や、相続人が不明な場合には、家庭裁判所を通じて相続財産管理人の選任を申し立てることが一般的です。義務化により、相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があるため、手続きの重要性が一層高まっています。
放棄された家を取得する際の具体的な手続きの流れ
放棄された家を取得するプロセスは、物件の状況や相続関係の複雑さによって異なりますが、基本的な流れは以下の通りです。
まず、対象となる不動産の登記簿謄本を法務局で取得し、現在の所有者や権利関係を確認します。次に、所有者が死亡している場合は戸籍謄本を取り寄せ、相続人の調査を行います。相続人全員が相続放棄をしている場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。
相続財産管理人が選任されると、債権者や利害関係者への公告期間を経て、最終的に国庫に帰属するか、または特定の申立人が取得できる可能性があります。取得希望者は、相続財産管理人や裁判所と協議し、適正な価格での買受けを申し出ることができます。手続きが完了すれば、所有権移転登記を行い、正式に所有者となります。
相続登記申請に必要な主な書類
相続登記を申請する際には、複数の公的書類を準備する必要があります。主な必要書類は以下の通りです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要です。これにより相続人全員を確定します。また、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票により、登記簿上の住所と死亡時の住所の同一性を証明します。
相続人全員の現在の戸籍謄本と住民票、遺産分割協議書がある場合はその原本と相続人全員の印鑑証明書も必要です。法定相続分で登記する場合は遺産分割協議書は不要ですが、特定の相続人が単独で相続する場合には必須となります。さらに、対象不動産の固定資産評価証明書も登録免許税の計算のために必要です。
書類の取得には時間がかかる場合があるため、早めの準備が推奨されます。特に古い戸籍謄本は複数の市区町村にまたがることもあり、郵送請求を含めて数週間を要することがあります。
相続登記にかかる費用の目安
相続登記には登録免許税や書類取得費用、専門家への報酬など、複数の費用が発生します。以下に一般的な費用の目安を示します。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% | 不動産の評価額により変動 |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 5,000円〜15,000円 | 相続人の数や取得先により変動 |
| 固定資産評価証明書 | 300円〜400円/通 | 市区町村により異なる |
| 司法書士報酬 | 50,000円〜100,000円 | 案件の複雑さにより変動 |
| 相続財産管理人の申立費用 | 予納金500,000円〜1,000,000円 | 裁判所が個別に決定 |
上記の費用はあくまで目安であり、不動産の評価額や相続関係の複雑さ、依頼する専門家によって変動します。特に相続財産管理人を選任する場合、予納金が高額になることがあるため、事前に裁判所や専門家に相談することが重要です。
価格、料金、または費用の見積もりはこの記事に記載されていますが、最新の情報に基づいていますが、時間の経過とともに変更される可能性があります。金銭的な決定を下す前に、独立した調査を行うことをお勧めします。
共有名義や複雑なケースでの注意点
放棄された家の取得において、共有名義や複雑な相続関係が絡むケースでは特別な注意が必要です。
共有名義の不動産では、共有者全員の同意がなければ処分や売却ができません。一部の共有者が行方不明の場合や相続放棄をしている場合、不在者財産管理人の選任や失踪宣告などの手続きが必要になることがあります。これらの手続きには時間と費用がかかるため、事前に専門家に相談することが望ましいです。
また、数世代にわたって相続登記が放置されている場合、相続人が数十人に及ぶこともあります。このような場合、相続人全員の同意を得ることは極めて困難であり、法定相続分での登記や遺産分割調停を検討する必要があります。
さらに、抵当権や差押えなどの権利が設定されている場合、これらの権利を抹消しなければ完全な所有権を取得できません。権利関係の調査は登記簿謄本だけでなく、固定資産税の納税状況や現地調査も含めて総合的に行うべきです。
まとめ
放棄された家の取得は、相続登記の義務化により以前よりも手続きが明確化されましたが、依然として複雑なプロセスを伴います。登記状況の確認から相続人の調査、必要書類の準備、そして登記申請まで、各段階で正確な手続きが求められます。費用面でも登録免許税や専門家への報酬など、一定の負担が発生することを理解しておく必要があります。共有名義や複雑な相続関係がある場合は、早期に司法書士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが成功への鍵となります。